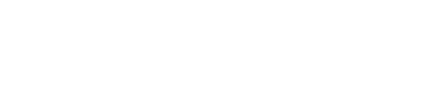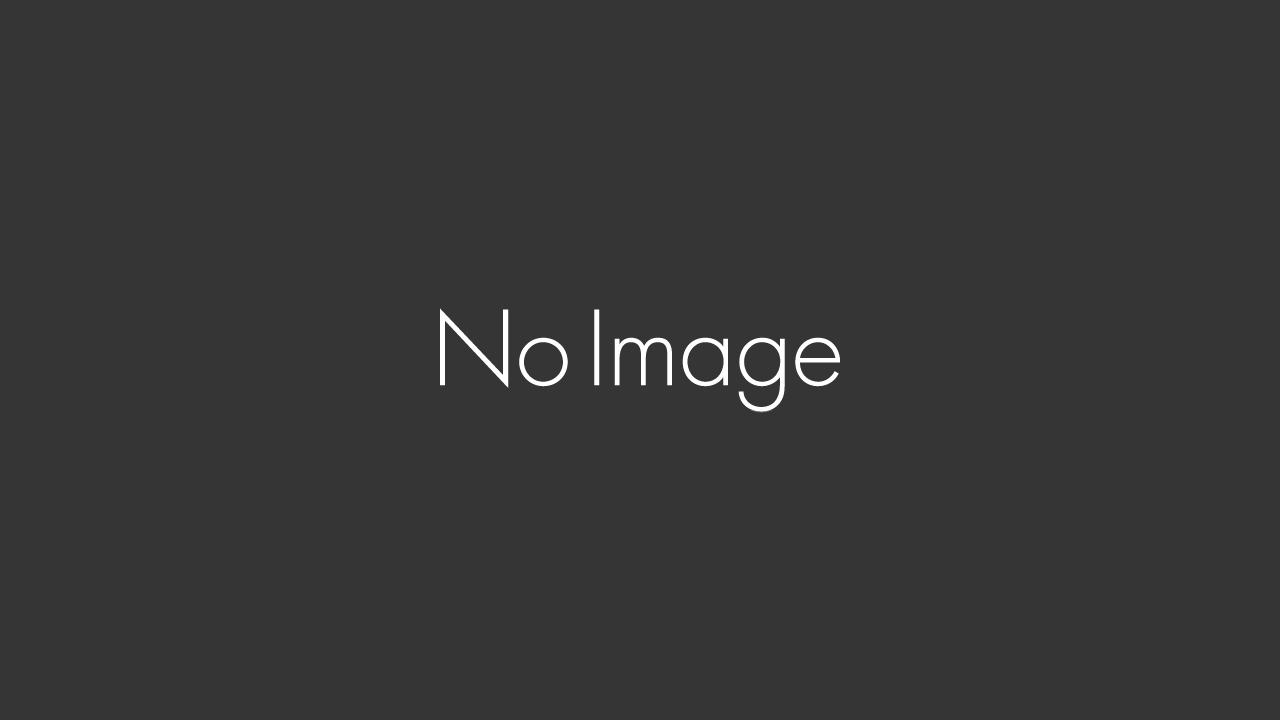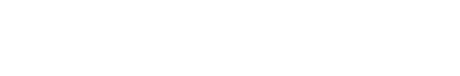発電設備や工場でよく用いられる「ラジエーター」。
名前はよく聞くけれど、どのような装置なのか、仕組みまで理解している方は多くありません。
この記事では、空冷式熱交換器としてのラジエーターの基本構造や特徴をわかりやすく、解説していきます。
そもそも、ラジエーターとは?
主に発電機や産業用エンジンなどの熱源機器において、冷却液の温度を下げるために使用される空冷式の熱交換装置です。
内部に銅やアルミなどでできたフィン付きのコイル(チューブ)を備えており、そのコイルの中を循環する液体(主に不凍液)をファンの風力で冷却します。
空気を熱源にして冷却を行うため、「空冷式熱交換器」とも呼ばれます。
ラジエーターは、冷却水を使わないため、水が確保しにくい場所や、冬季に凍結のリスクがある寒冷地での利用にも適しています。
近年では、非常用発電機や常用発電機のエンジン冷却に使われるケースが多いようです。
ラジエーターの冷却の仕組み
次に、ラジエーターはどのような仕組みで冷却液を冷やしているのかを確認していきましょう。
発電機や工場プラント設備で熱を吸収した高温の冷却液が、ラジエーターのフィンコイル(チューブ)と呼ばれる管の中を通っていきます。
そのフィンコイル(チューブ)の下、または上にファンが取り付けられており、外気があたってコイル(チューブ)内を通っていくことで液体が冷やされる仕組みです。
冷却液温度は運転条件によっては90℃前後になるケースもありますが、外気は夏場の猛暑時であっても、40℃前後に留まります。
空調設備や工場プラントで熱を吸収した冷却液は、外気の気温よりはるかに高くなっているケースが多く、ラジエーターを通る際に外気と間接接触することで、温度を下げて冷却することができるのです。
冷やされた冷却液は、再び空調設備や工場プラントの設備へと循環して、再び熱を吸収します。
熱を吸収して熱くなると、再びラジエーターに戻ってきて冷やされるという循環が繰り返されています。
ラジエーターの方式
ラジエーターの方式は、「押込通風型」と「吸込通風型」の2つがあり、それぞれ解説していきます。
押込通風型
押込通風型とは、冷却ファンがラジエーターの「手前」に配置され、外から取り込んだ空気を直接ラジエーターのフィン(熱を放出する薄い板)に向かって「押し込む」ように送る冷却方法です。
例えると、扇風機を体の正面に置いて風を当てるようなイメージです。
メリットは、冷たい外気を直接押し込むため、冷却効率が高いです。
吸込通風型
吸込通風型とは、冷却ファンがラジエーターの「後ろ(風下)」に配置され、ラジエーターを通過した空気をファンが「引き込む」ように吸い込むことで冷却する方法です。
例えると、窓から外の空気を吸い込む換気扇のイメージです。
メリットは、空気が均一に流れるため、冷却効率が安定します。
ラジエーターは空気流速を上げて伝熱効率を高める仕組みが取られており、そのため、強制通風装置として軸流ファンが設置されます。
ファンを管束(チューブバンドル)の手前に配置するのが押込通風型、後方に配置するのが吸込通風型ラジエーターです。
ラジエーターの構造
ラジエーターの構造はシンプルです。
一般的なラジエーターの場合、フィンコイル(チューブ)を組み込んだ塔体、軸流ファンなどから構成されています。
ノックダウン方式は、部品・ユニット単位で搬入することができ、現地での溶接も必要なく、ボルトだけで容易に組み立てられる方式です。
ラジエーターは伝熱効果を高めるために、熱交換部の管束の伝熱管の周囲にフィンを取付けたフィンコイル(チューブ)が採用されます。
伝熱管は被冷却流体の腐食性に応じて、材質を選んで採用することが可能です。
フィンコイル(チューブ)も性能が異なるので、どのようなフィンコイル(チューブ)を採用しているかが、ラジエーター選びの1つのポイントになります。
チューブでは、冷却液や周囲環境によりステンレスやチタンを選択することも可能です。
ただし、伝熱性能上サイズはかなり大きくなります。
まとめ:ラジエーターは空気を使った高効率冷却システム
ラジエーターは熱せられた冷却液を空気の力で冷やして再び使えるようにする装置です。
発電機や工場プラントの設備で冷却液が熱を吸収して熱せられ、その後ラジエーターのコイル(チューブ)を通っていく際に外気で冷やされ、温度を下げることに役立ちます。
近年では、常用・非常用発電機やプラント設備への導入が進んでおり、冷却効率・メンテナンス性・省エネ性能のバランスが重要視されています。
ラジエーターの選定にあたっては、使用環境や冷却液の性質に合わせた部品構成の検討が不可欠になります。
もし、ラジエーターの導入で悩んでいたら、弊社までご相談ください。