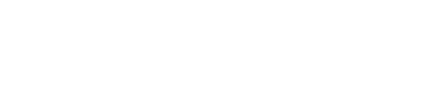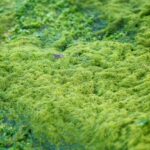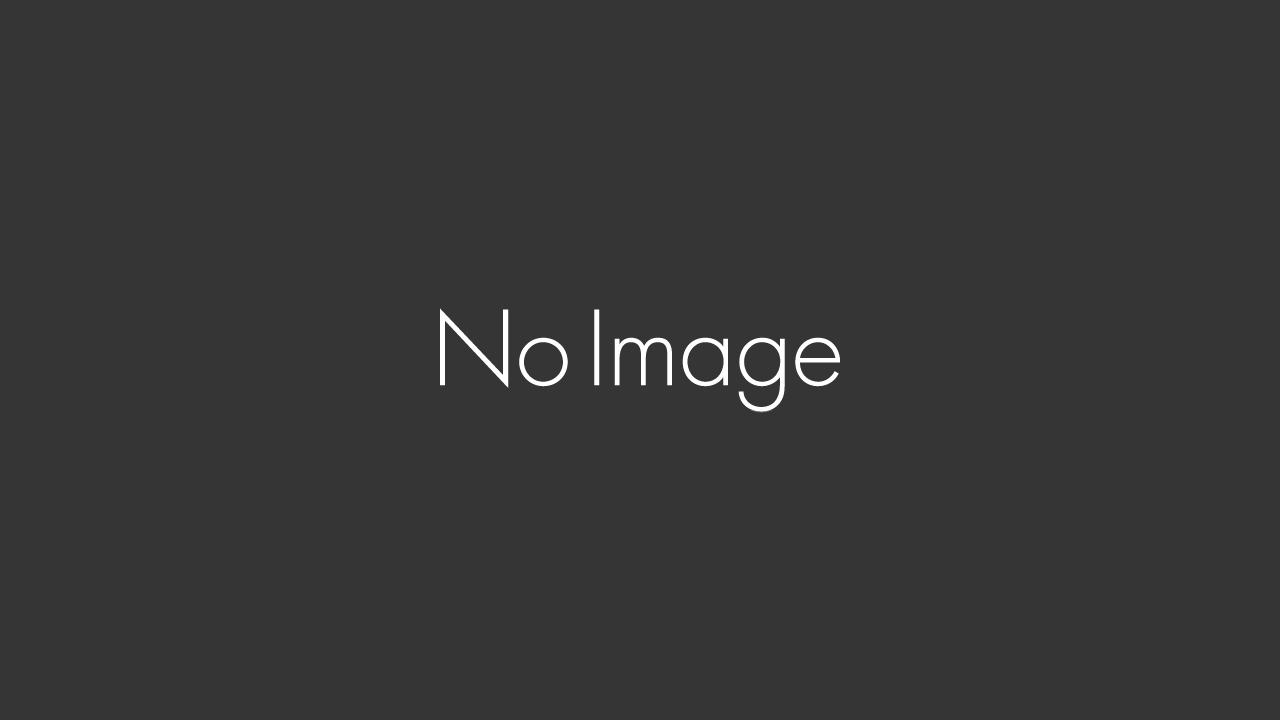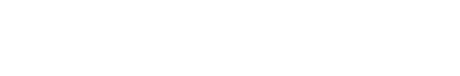冷却塔(クーリングタワー)は大型施設などにおける空調設備をスムーズかつ効率的に稼働させるうえで欠かせない装置です。
スライムとは、水中の細菌やカビなどの微生物が、自ら出した粘着物の中で増殖して、冷却塔の充てん剤や配管あるいは冷凍機のチューブ等に付着したものです。
ネバネバとした汚れのスライムは定期清掃によって除去するだけでなく、未然に発生を防止したいところです。
なぜ、冷却塔のスライム障害対策が必要なのか、スライムが発生する原因と被害、そしてスライムコントロール剤を用いた対策についてご紹介します。
スライムコントロール剤とは
スライムは冷却塔(クーリングタワー)の充てん剤や配管あるいは冷凍機のチューブ等に付着する汚れで、泥状の粘着物のことを指します。
簡単に言えば、ヌメリやヘドロのような汚れのことです。
冷却塔は外気湿球温度27℃では、入口水温が37℃で出口水温が32℃が標準的な設計基準となっており、微生物や菌の繁殖がしやすい温度環境となっています。
そのため、建築物衛生法では冷却塔の定期清掃や薬剤投与による殺菌などの衛生管理を行うことを義務付けています。
スライムコントロール剤は微生物由来のスライムを制御、抑制できる品です。
冷却塔(クーリングタワー)のスライム障害の3つの原因
冷却塔(クーリングタワー)のスライム障害が起こる原因として、代表的なものを3つご紹介します。
原因1.水と空気が直接接触
開放式冷却塔の場合、水と空気が直接接触するため空気中のゴミやガスなどの影響を受けやすくなります。
菌の増殖に最適な水温が37℃~41℃とされており、梅雨時期や夏場は冷却塔内が繁殖に最適な環境となってしまうので要注意です。
原因2.空気の汚染
開放式冷却塔は水と空気が直接接触する仕組みであるため、周囲の空気が汚染されていると冷却水が汚染され、塔内や配管などにスライムが発生しやすくなります。
冷却塔は有害物質を含む煙が立ち上る工場地帯に設置されている場合や、環境汚染が激しい都心のビルや排気ガスが激しい地方の幹線道路沿いの商業施設などの屋外に設置されるケースが少なくありません。
そのため、常に汚れた空気を取り込んでしまい、スライムの発生原因の一つとなってしまいます。
原因3.冷却水の不純物と濃縮
空気中の浮遊物や水に含まれる不純物などを取り込んで冷却水が濃縮すると水質が悪化するため、濃縮しないようにブローダウンを行い、補給水を加えてきれいな状態に保たなくてはなりません。
スライム障害により発生しうる3点の被害
ではスライムが発生・付着することで、どのような被害が起こるのか代表的な3つの被害を見ていきましょう。
被害1.冷却能力の低下
冷却塔(クーリングタワー)の充てん剤や配管あるいは冷凍機のチューブ等にスライムが溜まれば冷却塔の効率も低下します。
冷却水の効率が下がれば、熱源システム全体の性能低下につながります。
被害2.管の腐食
スライムが付着した管を通る冷却水の水質が悪化するだけでなく、管そのものにもダメージが加わります。
腐食して水漏れが起こるリスクや修理や交換などの手間やコストが発生するリスクも高まります。
被害3.管の詰まり
スライムは粘着性があり、大量に堆積するにつれ冷却水が流れにくくなり、詰まって使えなくなるリスクがあります。
冷却塔(クーリングタワー)のスライム障害の3つの対策
冷却塔(クーリングタワー)のスライム障害を防ぐにはスライム化が進むことやスライムが堆積することがないように定期的に清掃や換水を行うこと、
また、スライム障害が起こらないように未然に防止するには、スライムコントロール剤の投与が効果的です。
ここではスライムコントロール剤による対策法をご紹介します。
対策1.スライムコントロール剤による殺菌
殺菌タイプのスライムコントロール剤を断続的に投入する方法が、冷却塔のスライム障害対策のスタンダードです。
投入間隔は殺菌効果が持続される期間を目安としており、薬剤濃度や利用季節により異なりますが一般的に2~7日です。
スライムの表面に作用し、菌の数を減少させて壁面への付着や増殖を予防できます。
対策2.スライムコントロール剤による代謝効率の低下
スライムコントロール剤には成長途中のスライムに作用して、接液側のバクテリアを死滅させる殺菌効果だけでなく、死滅させることによってバイオフィルム内のバクテリアの代謝効率を低下させます。
バイオフィルムの成長を鈍化させることで、スライムの付着スピードを低下させることが可能です。
対策3.スライムコントロール剤による再発抑制
配管内などに発生するスライムやバイオフィルムなどの腐敗臭を伴うヌメリは、配管に付着したバクテリアやカビの繁殖を通じてもたらされるものです。
バクテリアやカビなどの微生物は季節や水温、pHなどにより発生や繁殖状況が変化します。
そのため使用・環境条件から殺菌タイプ、防腐・防カビタイプ、スライム除去タイプなどスライムコントロール剤の種類を見極め最適な薬品を投与することで、スライムの再発抑制にもつながります。
まとめ
冷却塔(クーリングタワー)内には空気から取り込んだ汚れや冷却水の不純物のな濃縮などが原因となり、ヌメリやヘドロ状のスライムと呼ばれる汚れが付着、堆積しやすい環境にあります。
スライムは熱源システム全体の性能低下や管の腐食や詰まりなどの被害をもたらすため、適切なスライムコントロール剤を用いてスライム障害対策を実施することが必要です。